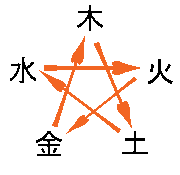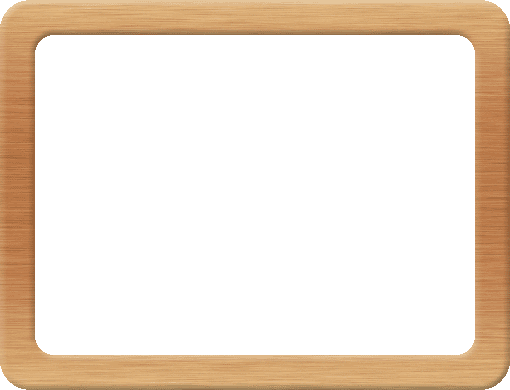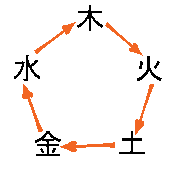秋はハイキングシーズン、山野に出かけることが多くなります
野山の探訪も、静かな古代史ブームも手伝って
蒲生野・紫香楽の宮跡(滋賀県)や斑鳩・平城京(奈良県)などなどへ、訪れる機会も出てきます
そこで思い浮かぶのは、奈良県明日香村のキトラ古墳です
直径約14mの二段築成作りの円墳で、7世紀末から8世紀初め頃に作られたと推測されています
1983年に、テレビカメラによる石室内の調査が行なわれ、玄武の壁画が発見され注目をあびました
高松塚以来の発見として、大々的に報道(1998年3月)されたことは、記憶に新しいところです
今回は、その「玄武」を含む「四神相応」について、辛草の雑記帳にデーター記載がありましたので
加筆訂正し、再編集してみました、従前のようにとりとめの無い内容に加え
皆様ご存知のことばかりで恐縮です、寛容なお心の方のみお進みくだされば幸いです
【 四神相応(しじんそうおう) 】 :四地相応(しちそうおう)に同じ
四神に相応じた最も貴い地相で次のようにされている
左方である東に流水のあるのを青龍(せいりょう、せいりゅう-とも)
右方である西に大道のあるのを白虎(びゃっこ)
正面である南に窪地のあるのを朱雀(しゅじゃく、すざく-とも)
後方である北に丘陵のあるのを玄武(げんぶ)
官位・福禄・無病・長寿を併有する地相で、平安京はこの地相を有するとされた (広辞苑 )
ところで、玄武とは西方をつかさどる白い虎神のことで
『四神』の一つで、四方位をつかさどる神のことです
また、土地には五神相応の相というのがあり、五神にふさわしい優れた地相をさします
東に流れがあるのを蒼龍、西に大きな道があるのを白虎
南がくぼんでいるのが朱雀、北に丘を背負うのを玄武
さらに、中央が平坦なのを黄龍といい、最良の地相とされています
私たちの回りには、このような五行や陰陽に影響を受けたものが色々あります
暦、干支(えと)しかり、相撲の土俵、都の造営、天文、幾何学、などなど
あらゆるものに関係しています
中国の戦国時代(前400〜前300年頃)において
陰陽説(いんようせつ)と五行説(ごぎょうせつ)と呼ばれる中国古代哲学が流行し
漢代(前200〜200年頃)に至って五行説は陰陽説と同化していきました
更に、五行相生と五行相剋の原理がとかれました
五行相剋:五行同士の闘争の相(ジャンケンと同じ法則)
・木は土に勝つ 木は土を剋し(土は木に養分を吸われる)
・土は水に勝つ 土は水を剋し(雨は土に染み込む)
・水は火に勝つ 水は火を剋し(火は水に消される)
・火は金に勝つ 火は金を剋し(金は火によって溶かされる)
・金は木に勝つ 金は木を剋し(木は刃物(金)で切り倒される)
五行相生:五行の循環
・木は火を生む 木は燃えて火を生み
・火は土を生む 火は灰から土を成し
・土は金を生む 土はその内部に金属の原石を内包し
・金は水を生む 金属板を良く磨くとその表面には水滴が生かび
・水は木を生む 水は植物を育てる
南アルプス 北岳(標高:3192m)
山行日:2001.08.16、(晴)
所在地:山梨県南アルプス市
旧芦安村
日本百名山に選定されている北岳
日本第2位の高峰で知られています
写真は北岳山荘からのもので
右方向に富士山があります
04:45登山開始
雪渓〜八本歯のコルを経由して
13:00に山荘に辿り着きました
カメラの方向に同じ百名山の一つ
間ノ岳(標高:3189m)があります
鈴北岳
山行日:2003.08.13、(晴)
所在地:滋賀県東近江市
旧永源寺町
この山は
御池岳(写真左奥方向)と
鈴ヶ岳(写真右方向)の中間にあり
御池岳登山のルート上にあり
鈴北岳単独の登山は
ほとんどありません
この写真は鞍掛峠方向からです
南宮山
山行日:2004.03.09、(晴)
所在地:岐阜県垂井町
ここは
天下分け目の争いで知られる
関ヶ原の合戦で
名義上は西軍の毛利勢が布陣した山です
南側から眺めました
合戦のあったところは
ずーと左側の方向です
東雨乞岳
山行日:2003.05.03、(晴)
所在地:滋賀県東近江市
旧永源寺町
東雨乞岳(標高1210m)は
雨乞岳(標高:1238m)の
前衛峰で眺望は360度
展望は思いのまま
相互の距離は約400m程
写真は
雨乞岳山頂からの東雨乞岳
なだらかな稜線です
山行に必要なものは
色々とありますが、大切なもといえば
食料、雨具、飲料水などなどですが
出来るだけ軽くしたいのが人情です
リーダーがいる山行では
ルートはお任せで、自分のいる所すら
解らないメンバーがいることがあります
さらには、行き先もわからないという
つわものもいるとか・・・・
自分の位置を知るためには
地図が役に立ちます
コンパスがあればなおなお結構
太陽が出ていれば、アナログの時計も
方角を知る上で非常に重宝です
地図やアナログ時計を持たない人は
時々リーダーに自分のいるところを
確認されてはいかがでしょうか
ついて行くのが関の山・・・・ですか
今回の写真は四神相応にちなみ
方角を冠した山をご紹介します
編集子オリジナル
| 五行相剋:同士の闘争 |
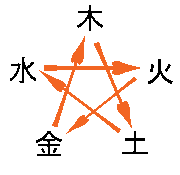 |
今日のことば
霊仙山 西南稜
山行日:2002.05.06、(晴)
所在地:滋賀県米原市
旧米原町
霊仙山には
いくつもの登山ルートがあります
紹介のルートは
南側の笹峠から取り付く西南稜です
稜線に上がると
頂上までの尾根ルートが視認でき
眺望も抜群です
陰陽五行思想は十干十二支と結びつき、さらに天文・気象をも取り込み、中国暦において
暦法・暦術へと進化し、易(えき)・卜筮(ぼくぜい)・八卦(はっけ)などへと変遷しました
このほか、中国に三世紀頃に伝来した仏教とも習合して、密教形成の要素ともなり
民間信仰にも影響を及ぼしました。
では、その八卦とはどのようなものなのでしょうか
八卦:周易で、陰陽の爻(こう)を組み合わせた八つの形象。自然界・人事界百般の現象を象徴
乾(けん):天を意味し、乾く・干す・水気のないさまや、太陽の光り輝く状態を示す(いぬい:北西)
兌(だ ):悦び解きほぐすという意で、沢が伸びて通る状態である
離(り ):常識的な語感とは逆に付着するという意味がある。明らかになる火の状態をあらわす
震(しん):ふるえる、動かすという意味から、雷が雨をともなって、あたりを震わすさま
巽(そん):譲り従う意味で、風に吹かれてそよぐさま、(たつみ:南東)
坎(かん):穴に陥ることで、水が穴に流れ落ちるさま
艮(ごん):止まる、留(とど)まるという意で、山のどっしりと動かない状態を示す、(うしとら:北東)
坤(こん):土、大地をあらわす、(ひつじさる:南西)
日本に、これらの思想が伝来したのは、七世紀初頭と推定されています
このうち、艮
(うしとら)は表鬼門としてあらわされます・・・・
※リンクをどうぞ
また、乾坤は乾坤一擲(けんこんいってき:運命を賭
(と)して、のるかそるかの勝負をする)などと
私たちの、人生を左右する言葉として使われます
相撲の行事が力士に「はっけよい、のこった」と掛ける声があります。「はっけ」とは『八卦』のことで
「よい」は『良い:いいぞ』のこと、「よい八卦になったぞ」、「よい八卦がでたぞ」という意味です
「のこった」はもちろん、『土俵にまだ余地が残っている』という意味で、時は十分で、戦うに十分
まだ土俵に余地があるから、しっかり取り組むよう、行司がうながす掛け声であるといわれます
これらの思想は、暦の普及につれて民間の生活の中に根を下ろし
IT革命が成された今日もなお、俗信・迷信として生き続けているのは、大変興味深いことです
だからといって、(日本人が忌み嫌う)友引の日に弔いを出したり、仏滅の日に結婚式を挙げるなど
強制や絶対視したり、排除や抵抗や無視したりするのも、大人げないものだと思います
一つの文化として認識し、その上で、お互いの幸せが訪れるように考慮されるべきものでは・・・・
※作成に当たっては、淡交社:陰陽五行、フリー百科事典:ウィキペディア、小学館:暮らしの中の仏教語、等を引用しました
521版:平成17年10月2日 日曜日
四 神 相 応
| 黒房 |
相撲の土俵:正面 |
青房 |
西
溜
り |
|
天地万物: 火 |
|
東
溜
り |
金
|
|
江戸城の造営:上野山 |
|
木
|
甲
州
街
道 |
|
平安京の造営:船岡山 |
|
平
川 |
山
陰
道 |
|
自然:丘陵 |
|
鴨
川 |
大
道 |
|
守護神:玄武(黒) |
|
流
水 |
白
虎 |
乾 |
十二支: 子 |
艮 |
青
龍
・
五
神
は
蒼
龍 |
酉
|
|
北・春 |
|
卯
|
西
・
冬 |
位置:中央
方角:天(外周:地)
季節:土用、守護神:黄龍
天地万物:土、色:黄色 |
東
・
夏 |
|
南・秋 |
|
| 坤 |
十二支: 午 |
巽 |
|
守護神:朱雀(赤) |
|
|
自然:窪地・湖沼 |
|
|
平安京の造営:小椋池 |
|
|
江戸城の造営:江戸湾 |
|
|
天地万物: 水 |
|
| 白房 |
相撲の土俵:向正面 |
赤房 |
山行に見る 山 の 方 角
一緒にいってみたいなこんなとこ
山葵の山行まっぷ
印の県に「目的地」があります
県名
福井
岐阜
山梨
滋賀
四神・五行 相関表
| 五行相生:五行の循環 |
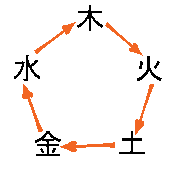 |
御在所岳
↓
国見岳
↓
釈迦ヶ岳
↓
西方ヶ岳
山行日:2005.09.02、(晴)
所在地:福井県敦賀市
敦賀半島の最高峰です
敦賀湾に
島のように浮かぶこの姿は
「敦賀富士」とも呼ばれ
信仰のお山です
八本歯のコル
↓
※ご参考までに
このコラムは
管理人のひとり言です
黒や灰色の文字は
編集子のオリジナル
カラー文字は編集子所蔵
資料からの引用です
山呼らいぶらり〜