
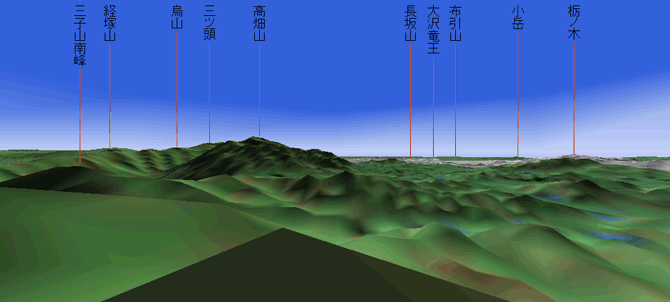
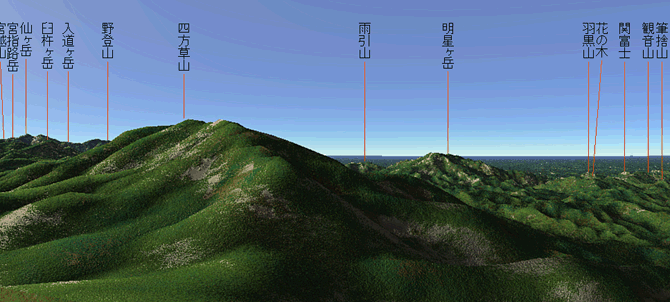

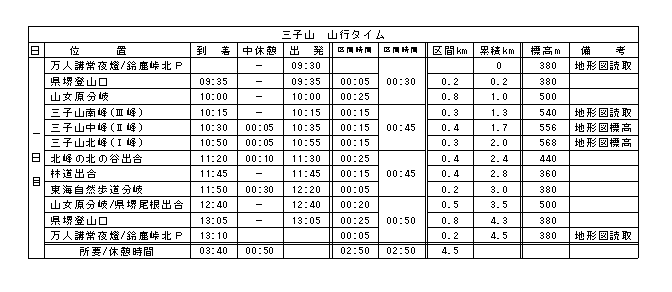
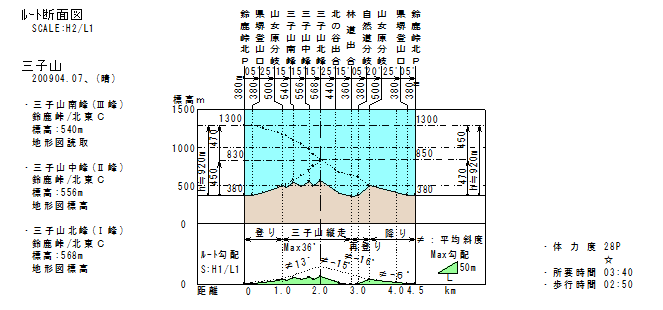
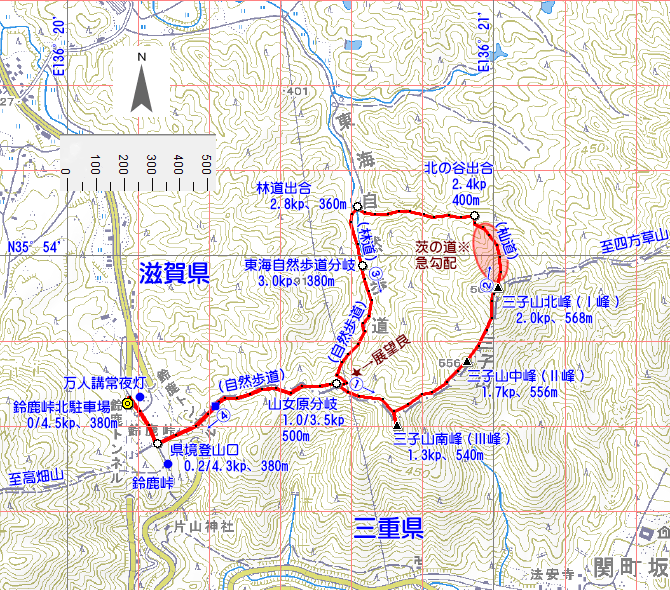
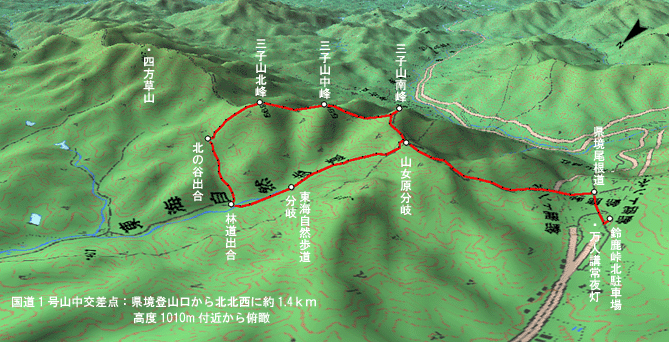
| 山行名 | 三子山 | |||
| 地 域 | 25zs:滋賀南鈴鹿 | |||
| 地図区分 | 1/20万地勢図:名古屋/亀山、1/25000地形図:鈴鹿峠/北東C | |||
| 山行年月日、(天候) | 2009.04.07、(晴) | |||
| 山名(よみかな) | 三子山南峰 (みつごやま―) |
三子山中峰 (みつごやま―) |
三子山北峰 (みつごやま―) |
― ― |
| 別名(よみかな) | 三子山Ⅲ峰 (みつごやま―) |
三子山Ⅱ峰 (みつごやま―) |
三子山Ⅰ峰 (みつごやま―) |
― ― |
| 所在地 |
土山町/関町 | 土山町/関町 | 土山町/関町 | ― ― |
| 中心地緯度経度 | 34.894628,136.346181 | 34.896634,136.348885 | 34.898957,136.350086 | ― ― |
| 標 高 | 540m | 556m | 568m | ― ― |
| 三角点 | 地形図読取 | 地形図標高 | 地形図標高 | ― ― |
| 点 名 | ― | ― | ― | ― ― |
| 展 望 | 無 | 無 | 東側 | ― ― |
| 登山道 | 遊歩道 | 明確登山道 | 北稜線:茨杣道 | ― ― |
| 登山口 | 34.893976,136.336804 | 下山口 | 登山口に同じ | |
| 最高/最低=標高差 | 568m/360m=208m | 総標高差 | 約920m | |
| 踏破距離 | 約4.5km | ポイント | 28P | |
| 斜度:勾配 | max36° | 体力度 | ★☆☆☆☆ | |
| 所要/歩行時間 | 所用03:40/歩行02:50 | ルート難度 | ★☆☆☆☆ | |
| 標準歩行時間 | 02:50+α(ルート難度) | 技術度 | ★☆☆☆☆ | |
| 山行目的 | 縦走 | アクセス難度 | ★★☆☆☆ | |
| 形態、山行人数 | 日帰り、2名 | 展望 | ★★☆☆☆ | |
| アクセス時間 | 自家用車、01:30 | 景観・風情 | ★☆☆☆☆ | |
| 駐車場 | 鈴鹿峠北山麓駐車場 | お薦め度 | ★☆☆☆☆ | |
| 備 考 | 北峰の北の谷稜線の道:茨道の急勾配 | |||
| ルート | 鈴鹿峠北P(09:30)~県境登山口~山女原分岐~三子山南峰/中峰/北峰 ~北の谷出合林道出合~尾根出合/山女原分岐~県境登山口~P(13:10) |
|||
| 概要 鈴鹿峠の東側に位置する三子山は、名前の如く南峰(Ⅲ峰)・中峰(Ⅱ峰)・北峰(Ⅰ峰)の三つの峰からなり、滋賀県と三重県の県境にその山塊を形成しています。展望は、北峰の東側と高圧鉄塔の箇所からしか望めません。北峰からの尾根伝いの先には、四方草山・霧ヶ岳・安楽越へと続きますが、鈴鹿において一・二を争う危険箇所でもあります。大和朝廷ができた頃、鈴鹿の関所(天下三関)が設けられていました。都が平城京に移ると、鈴鹿山脈を越えて近江に入る道が必要になり、鈴鹿越えの東海道が設けられ、江戸時代に宿駅が整備され、現在の大動脈の一つとして重要な位置を占めています。一般的には、この峠から西側を南鈴鹿と呼ばれています(本hpでは武平峠から西を南鈴鹿としています)。今回は北峰までのピストンの予定でしたが、北の谷の急勾配を下り、東海自然歩道を登り返すコースを新しく見つけました。これが茨の道でした・・・・ | ||||
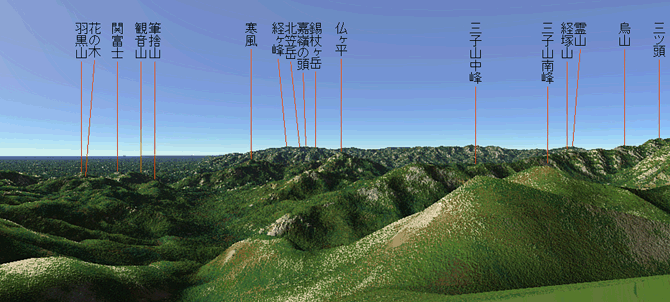
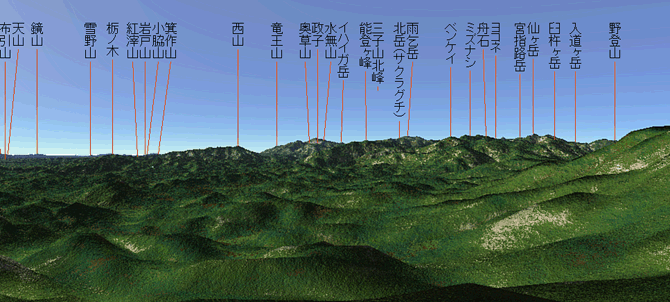
| ルート・シュミレーション |