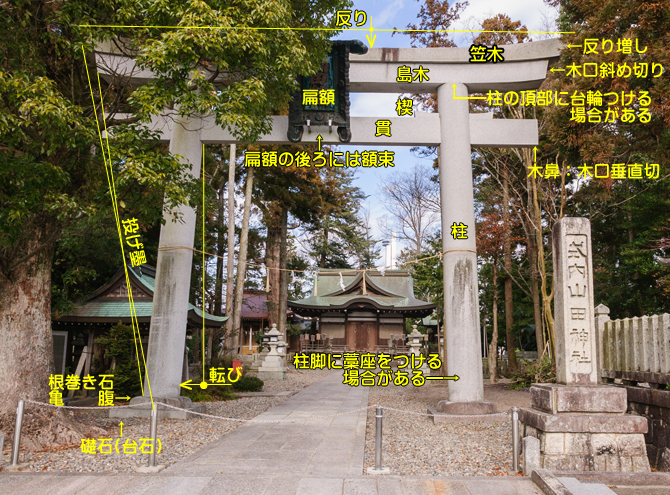| 形式による分類 |
| 形 式 |
種 類 |
特徴等 |
参考写真(図) |
神明系
(島木無し
額束無し
笠木に
反り無し) |
神明鳥居
(しんめい―) |
神明系鳥居の標準形
すべて丸太状で構成されている
笠木が丸状で反りが無い、両端垂直
貫は丸状で柱から突き出ない、楔はない
柱は円形で転び無し
直線的な鳥居
一般的に笠木の元口は正面右側(以下同) |
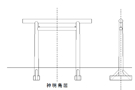 |
白木鳥居
(しらき―) |
神明鳥居の形に同じ
すべて丸太状で構成されている
樹皮をはいだ白木を用いる
歴代天皇の御陵に多く使用される
素木(しらき)鳥居とも呼ぶ
本hpでは
加工されていないものを素木鳥居と呼ぶ |
 |
黒木鳥居
(くろき―) |
形は神明鳥居と同じ
最も原始的で素朴な鳥居
樹皮がついているままの生木を用いる |
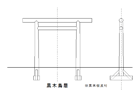 |
靖国鳥居
(やすくに―) |
靖国神社の鳥居を代表とする
笠木が丸状で反りが無い、両端垂直
貫が長方形で柱から突き出ない
柱は円形で転び無し |
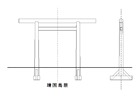 |
鹿島鳥居
(かしま―) |
鹿島神宮の鳥居を代表とする
笠木が丸状で反りが無い、両端斜め切
貫が角型で柱から出て楔つき
笠木に素木を用いる場合元口は正面左
(一般的には、元口は正面右側)
柱は円形で転び無しまたはあり |
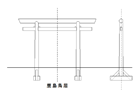 |
宗忠鳥居
(むねただ―) |
京都の宗忠神社にある鳥居を代表とする
鹿島鳥居に額束をつけたもの
笠木の両端を斜め切り
貫は角型で柱から出て楔つき |
 |
伊勢鳥居
(いせ―) |
伊勢神宮の鳥居を代表とする
笠木が五角形で反りが無い、両端斜め切り
貫は角柱状で柱から突き出ない、楔がある
柱は円形で転び無し
※写真は特殊型:楔無し、柱転び付 |
 |
内宮源鳥居
(ないぐうげん―) |
すべて角材で構成されている
柱が八角形が特徴
笠木は五角形で反りがなく、両端斜め切り
貫は角柱状で柱から突き出ない、楔有
伊勢鳥居の変形 |
|
外宮宗鳥居
(げくうそう―) |
伊勢鳥居の変形
島木がある(笠木より幅が広い)、両端斜め
柱は円形や八角形のものもある
※内宮源鳥居と混同されている場合もある |
|
伊香式鳥居
(いかしき―) |
伊香具神社にある鳥居を代表とする
神明形式を基本とする
三輪式鳥居と両部鳥居を組み合わせた形
神明系の三輪鳥居に八本の稚児柱を設ける |
 |
| |
|
|
明神系
(島木有り
額束有り
笠木に
反り有り) |
明神鳥居
(みょうじん―) |
明神系の標準的な鳥居
笠木と島木を曲線的に反らせる
笠木・島木共に、両端斜め
貫が柱から突き出し、楔つき
柱は転び(内側に少し傾斜をつける)つき
柱脚に亀腹がある場合がある
島木鳥居を代表する |
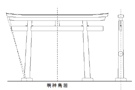 |
根巻鳥居
(ねまき―) |
明神鳥居の柱の根元に藁座を設けたもの
「板」や「竹」などの別の材料で巻く
巻きつけた部分を黒く塗る場合もある
柱の下部が腐らないようにするため |
|
台輪鳥居
(だいわ―) |
明神鳥居に台輪を設けるたもの
島木と笠木に反り増しがある
貫が柱から突き出し、楔つき
柱の頂部と島木の接続部分に台輪を置く |
 |
稲荷鳥居
(いなり―) |
笠木と柱の根元を黒く塗り、他を朱色に塗る
他は明神鳥居に同じ
台輪をつけたものもある |
|
春日鳥居
前期型
(かすが―) |
春日大社にある鳥居を代表とする
笠木と島木に反りがなく、両端垂直切
貫が角型で柱から突き出ていて楔つき
柱転び有りまたは無し
春日大社の独自の形 |
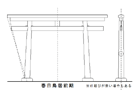 |
八幡鳥居
前期型
(はちまん―) |
春日鳥居が進化して
島木と笠木に反りがなく
笠木斜め切り、島木垂直切り
貫は角型で柱から突き出ていて楔つき
柱転び有りまたは無し |
|
春日鳥居
後期型
(かすが―) |
八幡神社前期型が進化して
島木と笠木に反り増し
笠木斜め切り、島木垂直切
貫は角型で柱から突き出ていて楔つき
柱転び有りまたは無し
木部彩色 |
|
八幡鳥居
後期型
(はちまん―) |
八幡鳥居前期型が進化して
島木と笠木に反り増しがある
笠木斜め切り、島木垂直切り
貫は角型で柱から突き出ていて楔つき
柱転び有りまたは無し
木部彩色なし
島木木口が斜めとなり
進化して明神鳥居となる |
|
両部鳥居
(りょうぶ―) |
四脚鳥居・権現鳥居・宮島鳥居
袖鳥居・脇差鳥居など呼称
島木と笠木に反り増しがある、両端斜め切
貫は角柱状で柱から突き出ていて楔つき
柱の前後に稚児柱を持つ
台輪を持つものもある
笠木に屋根を設ける場合もある
柱の転び有りまたは無し |
 |
三輪鳥居
(みわ―) |
大神(おおみわ)神社にある鳥居を代表する
島木と笠木に反り増しがある、両端斜め切
貫が柱から突き出ている
左右に副柱※がある
※明神鳥居の左右に脇鳥居をつけたもの
三つ鳥居とも呼ばれる
柱に転びは付けない
他にも三光鳥居・子持鳥居とも呼ばれる
奈良の檜原神社には入口三か所に扉付 |
|
山王鳥居
(さんのう―) |
山王神社にある鳥居を代表とする
島木と笠木に反り増しがある、両端斜め切
貫が柱から突き出ている
上部にむな束に扠状に破風と裏甲がつく
(明神鳥居の上に破風をつけたもの)
山王の教えと文字を形にしたものといわれる
合掌鳥居・日吉鳥居・破風鳥居とも呼ばれる |
|
総合鳥居
(そうごう―) |
山王鳥居に台輪をつけたもの
破風の頂部に烏頭(からすがしら)を設ける
台輪を設ける |
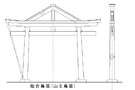 |
奴禰鳥居
(ぬね―) |
台輪鳥居の額束に
合掌状の破風扠首(さす)束をはめている
山王鳥居の変形で笠木上の合掌はない |
|
中山鳥居
(なかやま―) |
岡山の中山神社にある鳥居を代表とする
島木と笠木に反り増しがある、両端斜め切
貫は角柱状で柱から出ない
明神鳥居の貫が柱から出ないもの |
|
宇佐鳥居
(うさ―) |
宇佐神宮の鳥居で額束がない
笠木に桧皮葺の屋根をかける
貫は角型で柱から抜ける、楔つき
台輪・藁座をつける
台輪鳥居が基本 |
|
住吉鳥居
(すみよし―) |
大阪の住吉神社を代表とする
柱が四角形
他は明神形式の特徴を持つ |
|
城南宮鳥居
(じょうなんぐう―) |
基本形は明神鳥居
笠木の上に屋根を葺く
棟の部分に笠木・島木を重ねる
島木の正面中央に神紋の金具がうたれる
柱下に亀腹(饅頭)がある
伏見の城南宮にある |
|
越前鳥居
(えちぜん―) |
台輪鳥居の笠木が二層になったもの |
|
弥彦鳥居
(やひこ―) |
両部鳥居の台輪に屋根をつけたもの
新潟県の弥彦神社にある |
|
唐破風鳥居
(からはふ―) |
笠木・島木が唐破風型をしている
木口垂直
柱に転び無し
貫は柱を貫通、楔無し
三上山に多くあった鳥居で御上鳥居とも言う |
|
| |
|
|
明神系
島木無 |
筥崎鳥居
(はこざき―) |
福岡の筥崎神社を代表する
明神鳥居を原型とし
笠木の両端が跳ね上がった特徴のある形
笠木は島木を兼ねる
柱が三段になってい太い場合もある
柱が角型になる場合もある |
|
肥前鳥居
(ひぜん―) |
肥前国の鳥居の独特の形で石造
笠木の先端が大きく反る
笠木は島木を兼ねる
柱は下に行くほど太くなる
笠木・島木・柱は三本つなぎ
貫は柱を貫通し楔はない
台輪がある |
|
| |
|
|
| 特殊系 |
三柱鳥居
(みはしら―) |
上部から見て三角形になるように
三角形の向きは
日月の昇降や三位の神裡に合わせている
貫は柱の外に出ない
柱は円形や多角形があり、転び無し
神明・明神系ともにある |
|
注連縄鳥居
(しめなわ―) |
二本の柱に注連縄を渡しただけのもの |
|
多額束鳥居
(たがくつか-) |
額束が複数本あるもの |
|
貫無し鳥居
(ぬきなし−) |
柱と笠木だけのもの |
|
冠木鳥居
(かぶき―) |
冠木門に注連縄を渡したもの |
|
冠木両部鳥居
(かぶきりょうぶ−) |
冠木門に稚児柱が設けられたものに注連縄 |
|
| |
|
|