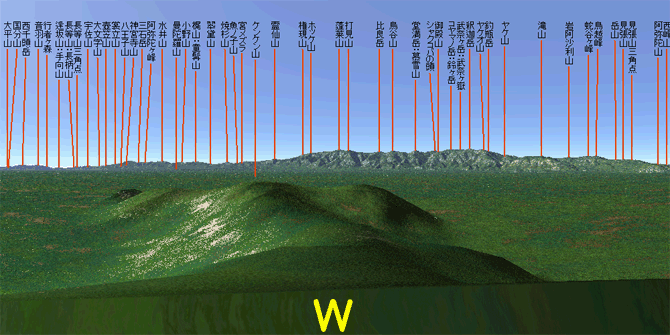
| ルート・シュミレーション |
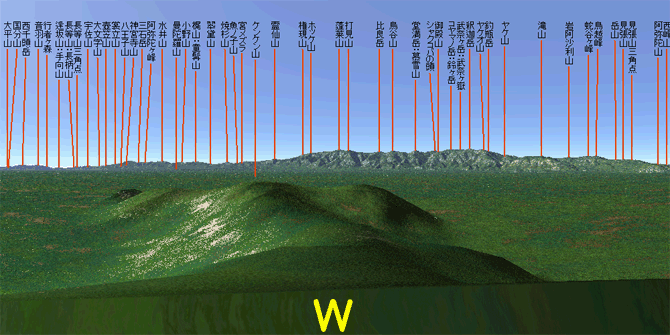
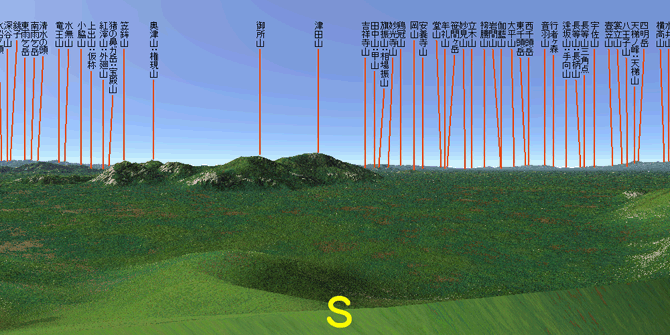
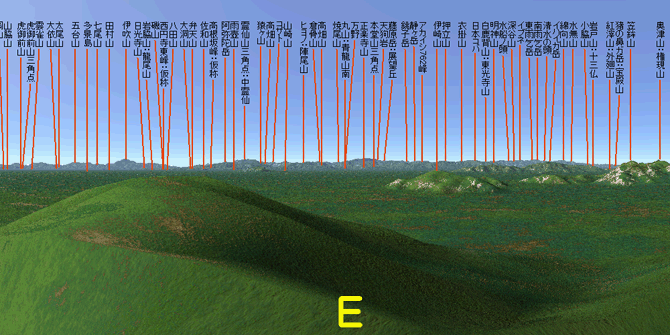
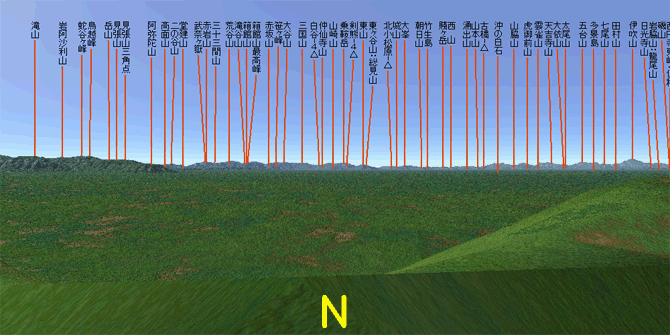
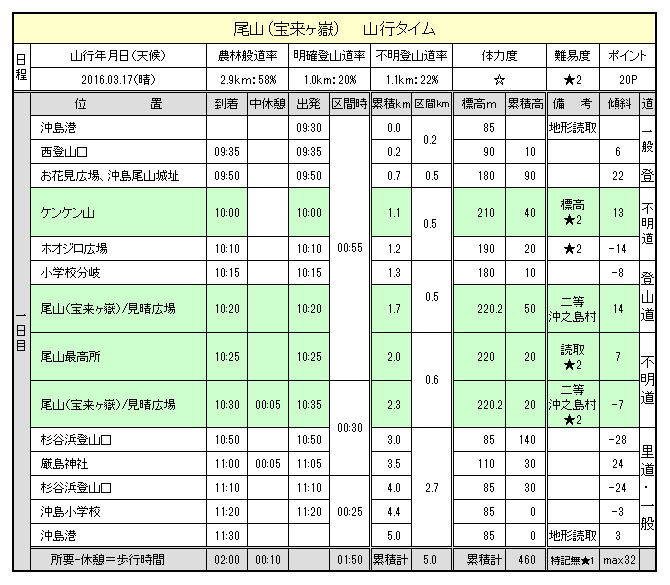
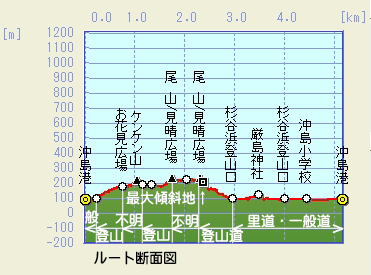
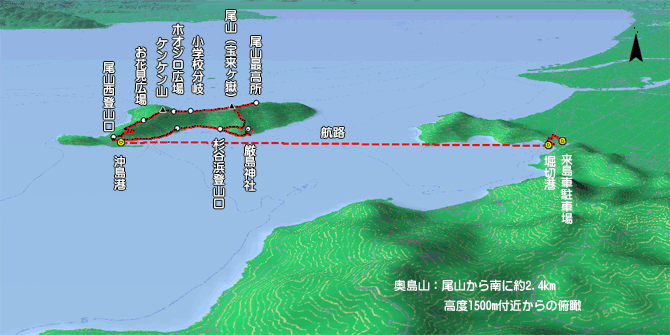
| 山行名 | 尾山(宝来ヶ嶽) | |||
| 地 域 | 25en:滋賀湖東-北部 | |||
| 地図区分 | 1/20万地勢図:名古屋/近江八幡、1/25000地形図:沖島/南東NW | |||
| 山行年月日、(天候) | 2016.03.17、(晴) | |||
| 山名(よみかな) | 尾 山 (おやま) |
ケンケン山 (けんけんやま) |
頭 山 (あたまやま) |
― ― |
| 別名(よみかな) | 宝来ヶ嶽 (ほうらいがたけ) |
見景山 (けんけんやま) |
― ― | ― ― |
| 所在地 |
近江八幡市 | 近江八幡市 | 近江八幡市 | ― ― |
| 中心地緯度経度 | 35.207751,136.066137 | 35.206268,136.058722 | 35.199675,136.053143 | ― ― |
| 標 高 | 220.2m | 210m | 130m | ― ― |
| 三角点 | 二 等 | 地形図標高 | 地形図読取 | ― ― |
| 点 名 | 沖之島村 | ― | ― | ― ― |
| 展 望 | 山頂:南方向 | 山頂:なし | ― ― | ― ― |
| 登山道 | 明確登山道 | 不明登山道 | 未踏跡 | ― ― |
| 登山口 | 35.200973,136.055245 | 下山口 | 35.204865,136.065159 | |
| 最高/最低=標高差 | 220m/85m=135m | 純標高差 | 約460m | |
| 踏破距離 | 約5.0km | ポイント | 20P | |
| 斜度:勾配 | max28° | 体力度 | ★☆☆☆☆ | |
| 所要/歩行時間 | 所要02:00/歩行01:50 | ルート難度 | ★★☆☆☆ | |
| 標準歩行時間 | 02:00+α(ルート難度) | 技術度 | ★☆☆☆☆ | |
| 山行目的 | 峰探訪/島内散策 | アクセス難度 | ★☆☆☆☆ | |
| 形態、山行人数 | 日帰り、1名 | 展望 | ★★☆☆☆ | |
| アクセス時間 | 自家用車/船、01:00 | 景観・風情 | ★☆☆☆☆ | |
| 駐車場 | 来島車:無料駐車場 | お薦め度 | ★☆☆☆☆ | |
| 備 考 | 船のダイヤ確認必要、ケンケン山及び尾山から東の峰:藪 | |||
| ルート | 来島車P(08:55)〜堀切港(19:05/09:15)=船=沖島港(09:25/09:30) 〜尾山(10:20/10:35)〜厳島神社〜港(11:30/12:00)=船=P(12:10) |
|||
| 概要 尾山は標高こそ低いのですが、船で行く山としてユニークな存在です。沖島には、頭山(あたまやま、かしらやま)、ケンケン山(見景山)、尾山(宝来ヶ嶽など)からなる歴史の多い島で、東西約2.5km、南北約1.0kmの大きさです。戦国時代には、堅田衆と共に水軍があったと伝わります。湖にある島に、人が永住しているのは世界的にも珍しく、約124世帯、330人程度の島民がいて(平成25年度)、主に漁業を生業としています。島を形成しているのは、良質の石材で、江戸中期には、漁業の他、石材の産地としても知られていました。明治期に入り、琵琶湖疏水、南郷洗堰、鉄道建設などに切り出されましたが、現在はその歴史に幕が下ろされています。大正時代に海底から奈良時代の古銭が引き上げられ、その時代から島には住人がいたという証でしょうか。元気な高齢者が多いのも特徴で、都会では失われたコミュニティーが残されているようです。 | ||||